竹内好かく語られ記
熱っぽい著者の息吹 ―竹内好著『中国を知るために』(全三冊)―
Tweet
熱っぽい著者の息吹 ―竹内好著『中国を知るために』(全三冊)―
勁草書房 田辺貞夫
吉祥寺の竹内家には、(竹内好〉の表札が在りし日のままにかけられている。玄関を入ってすぐの居間兼応接間に、いつもにこやかに笑っている竹内さんの肖像写真がおかれてあり、私はいまだにその前に坐る度に、「どうした、少しは編集ということがわかるようになったかい」と問われているような気がする。
竹内さんに初めてお会いしたのは、昭和三十七年の秋、私が普通社という出版社の編集部にいた頃だった。当時、普通社では社長の八重樫昊の発案で、社の母体を作るために「日本のなかの中国」という出版が企画され、そのための研究会が重ねられていた。この会の中心メンバーが、竹内好、野原四郎、安藤彦太郎、新島淳良、尾崎秀樹、橋川文三、野村浩一、今井清一、飯倉照平……といった人々だった。神楽坂の出版クラブで行なわれていたその会合に、社長のお供で出席したのが、竹内さんに会った最初だったと思う。

この中国問題研究会(通称・普通社の会)が続くにつれて、当初企画されていた単行本とは別に、叢書のシリーズ刊行と、その付録として小型の雑誌をつけるプランが生み出され、次第に具体化してきた。雑誌の名が『中国』、叢書の名が「中国新書」、研究会の名が「中国の会」と決まったのは、三十七年の十一月頃だった。新書の企画は膨大なもので、書下しを中心に、絶版になっている名著の復刊も含むということで、およそ五十点におよぶリストが決まり、雑誌もB6判を横に使った、食べ物雑誌『あまカラ』に似た趣味的なスタイルがとられることになった。雑誌編集の実務担当者として、竹内好、橋川文三、尾崎秀樹の三氏がえらばれ、飯倉照平さんがそれを手伝うことになった。この頃、竹内さんは日本橋にあった普通社の事務所へ打合せに見えることもあった。
『中国を知るために』は、その雑誌『中国』に連載されたエッセイである。その第一回を竹内さんはこう書き出している。「「中国を知るために」という題で、これからしばらく連載を書くことになった。実をいうと、何を書くかはまだ決めかねている。当分連載をつづけることだけが決まっていて、内容はまだ決まっていない。書いていくうちにおのずと形式が決まり、形式にしたがって内容が決まっていくだろうという、至極のんきな、また無責任といえば無責任な、あやふやなところから出発するわけだ。心もとない気がしないではない。……」
こうした姿勢でスタートしたエッセイだが、回を追うごとに、竹内さんの雑誌にかける情熱が反映して、力のこもった一文となり、次第に『中国』の柱となっていった。
内容は、〈支那と中国〉〈度量衡のはなし〉から〈もちの話〉、〈習俗と美意識〉など千差万別、書きぶりも自由無碍の筆致だが、そこには、熱っぽい著者の息吹が感じられた。それだけにわずか一回分一二、三枚の原稿だが、一朝一夕にはならず、時に苦行の日々を経験されたようだ。雑誌の編集にあたった、その時々の担当者の話からもそれは伺われた。そういったことからも本書は決して、私が編集したとはとてもいえない。本書の成立ちには、その生みの段階で協力した多くの人々(例えば、『中国』歴代の編集長)の努力があり、私はただその成果をまとめて本にさせていただくお手伝いをしたに過ぎない。ただ前に述べたような事情で、最初の時期から中国の会に関係してきたという縁《えにし》で……。
これは、竹内さんの〈けじめ〉を大切にする人柄のおかげでもあるのだ。『中国を知るために』がかなり話題になるようになってから、他の出版社などからの話もあったようだが、「これは当初から君の処でという約束だから」と一顧だにされなかったものだ。
だからこの『中国を知るために』(第一―第三集)の編集発行には、苦しい思い出はほとんどなかったといってよい。それどころか、竹内さんに会い、中国の会の人々に接することで、どれほど多くのことを教えられたかしれない。今でも私に関係の深い著者の多くはその時期に知り合った人々である。
今年(昭和五十三年)は日中友好条約の締結も成り、政治的にも、民間ベースでも、日中間の人的交流は一層賑やかになっている。日本が二十七階の貿易センターを建てるとか、中国から一万人の留学生が来日するとか、話題はつきない。こうした情勢によって、ますます「私は中国を知った」と思う人々が増えることだろう。竹内さんが警告したのはそこのところである。
日本人は、多くの人がそれぞれ「私は中国を知っている」と何となく思いこんでいる。私達はみな、中国人と同じ髪の色、肌の色であり、よく似た顔かたちをしている。日常に使う文字は中国から輸入したものであり、いまでも共通のものが多い。平仮名や片仮名も原型は漢字だ。風俗、文化、生活習慣、ものの考え方などで中国伝来のものは数しれない。よく日本と中国は同文同種だといわれている。たしかに普通の外国人が知らない中国を私たちは知っている。あるいは知っているつもりでいる。じつはここに問題があるのだ、と竹内さんはいう。同文同種の隣人同士だから話は通じやすい、などと思ったらとんでもない。かえって理解のさまたげになるだけだ。たとえば、中国語を習うのに、私は漢文を読めるという自信が、逆に学習の能率をおとす。また基本的な考え方の型がちがう、数の観念がちがう、同文同種は迷信でしかない。事実はむしろ異文異種ではないかと。
こうした「日本人の立場から中国を知ろう」とする態度で貫かれたそれぞれの文章が、サロン的に、気楽に、ゆきつ、もどりつ、立ちどまりつの調子で書かれている。しかし、その底には、無知でいながら、あるいは無知のために思いあがっている人々に対する深い怒りが感じられる。同時に楽しみながら、一つ一つの文章を大切に考えて、明るいゆとりをもって書いているようでもある。
三十八年の二月から三月にかけて、中国新書の最初の三冊(竹内好『現代中国論』他)、五月から六月にかけてつぎの三冊(武田泰淳『わが中国抄』他)が刊行された。雑誌『中国』もその付録としてはさみ込みの形で出版された。
付録としての雑誌『中国』の編集は、中国新書の刊行計画と見合って、三号分ずつまとめて進められていた。神田三崎町の東光ビル内に一室を借りて会合したのもこの頃であった。ところが、この年の九月になって、普通社は、他の企画の失敗で経営不振におちいり、新書と雑誌の続刊が不可能になった。このときのことを竹内さんは、日記にこう記している。
「当分カゼで引きこもっていたが、仕事のあとで気ぬけしているので、その割には能率があがらない。そんな一日、尾崎秀樹君が急用でたずねてきた。普通社が、漫画雑誌の失敗で穴をあけて、親会社の平凡社から出版を中止しろと命ぜられたので、「中国新書」がストップになった。……これは思いがけない事件だった。「中国新書」は予定よりはおくれているが、一回三冊、二回計六冊を出版して、三回目が進行中だし、それに見あって雑誌『中国』の方も編集が進んでいる。ここまで来てやめるといわれたんじゃ困る。寝耳に水だ。中国の会としても恰好がつかない。といって、話をきいてみれば、強く推せない事情も了解がつく。尾崎君は、本の方はともかくとして雑誌だけは自前でもつづけたいという意見だ。私としても、このままやめたんでは、みっともないという点では同意見だが、さて自主刊行となると、相当に金とひまを食うので、すぐには決断がつかない。」
この前後、私にとってもあわただしい日々がつついた。八重樫社長が事情をしたためた封書を持って、執筆を承諾されていた中野重治氏や榊山潤氏のお宅を訪ねたり、普通社としての最後の中国の会の集まりを新宿の〈玄海〉でもったことなどを想い出す。
いくつかの曲折をへて、三十八年の暮、中国新書は、既刊分を含めて一切が勁草書房に移ることになり、雑誌『中国』は中国の会の自主刊行となった。そして私は新書とともに勁草書房へ移ることとなった。
『中国』は、第七号を三十九年六月に「新出発準備号」と名づけて出し、その後四十二年十一月の第四八号まで、三年六ヵ月のあいだ自主刊行をつづけたが、四十二年十二月より徳間書店の発行に変った。そして四十七年十二月、一一〇号で休刊するまで、あしかけ十年にわたって刊行されたのである。
連載エッセイ『中国を知るために』は、その間、第一四号(田中メモランダム)、第二五号(朝鮮)、第四二号(分裂)などいくつかの例外を除いて、毎号休むことなく執筆された。計一〇二回になる。
当初の計画では、ある程度まとまったところで中国新書に編む予定だったが、いろいろの事情から、中国新書は、十一冊目の『現代中国入門――本による中国案内――』を最後に休刊となっていたので、第一回から三四回までを収めた『中国を知るために』第一集は、四六判カバー装の単行本として発行された。昭和四十二年二月のことである。
この巻には、竹内さんの希望で、巻末に「『政治に口を出さない』の弁」「ふたたび『政治に口を出さない』の弁」の二つの短文(東京新聞掲載)が収めてある。これは、中国の会のとりきめ(第二項)についての見解を述べたものだった。ここで、中国の会と雑誌『中国』のとりきめ(暫定案)を記しておきたい。
一、民主主義に反対はしない。
二、政治に口を出さない。
三、真理において自他を差別しない。
四、世界の大勢から説きおこさない。
五、良識、公正、不偏不党を信用しない。
六、日中問題を日本人の立場で考える。
雑誌が自主刊行になってから、中国の会の事務所も水道橋、中野、代々木駅前、そして同じ代々木でも岸田劉生ゆかりの碑などがある、駅より十分ほどの処へ移って、そこが最後の地となった。
代々木の駅を出て、会の事務所のある新宿方向へ坂を下ってゆく途中に、白紙堂という古本屋があった。そこの棚には『中国』のバックナンバーが並んでいた。おやじさんは橋川文三氏をよく知っているといっていたが。
竹内さんは、仕事に厳しく、気難かしい人物とうけとられていたが、私の接するところ、本当に和やかで心の広い人柄だった。代々木の事務所で話をしていて、よく昼時になってしまい、居合せた人達と一緒に食事に出たことがあったが、そんなとき、いつも先に立って新しい店に案内するのが竹内さんだった。「若い人は無精で、いつも手近ですませるようだがね」などといっていた。
また、あの左党の竹内さんにこんなこともあった。たまたま神戸大学の山口一郎さんが一緒で、他に橋川さんや飯倉さんもいたと思う。打合せの後で、お茶でも飲もうか、と歩いていた竹内さんが、いきなり甘味処とのれんの出た〝しる粉や〟に入ろうという。皆がびっくりすると、「これは山口さんと田辺君へのサービス」といって笑いながら入ってしまった。これは後で誰に話しても信じてもらえなかったものだ。
私にとって、一週間に一、二度中国の会の事務所に寄っては、竹内さんや他の人々と話をすることは、何か一つの安息といった感じだった。そうした気持で訪れる人達は他にも多いらしく、狭い事務所は、いつも青年達の熱気がこもっていた。
そうしているうちに昭和四十五年三月、私は竹内さんにお願いして『中国を知るために』第二集をまとめさせていただいた。先の第一集の装幀が、濃いセピアを基調にした地味なものだったので、今度は上製函入で原色を使い、普通社時代から知合いの画家にカットを依頼してアクセントをつけた。
その第二集が、その年の十一月、第二四回毎日出版文化賞を受賞したのである。この受賞の対象には、書物に加えて、長年に亙る中国の会の活動も含まれていることと私は思っている。
さて、受賞は決まったが、竹内さんは人も知る賞ぎらい、はたして受けていただけるかと、当日会場に現われた姿を見るまでヒヤヒヤしたものである。この受賞を機に、先に刊行した第一集も上製函入に改め、装幀もシリーズ風にそろえて、第二集とあわせて発行したが、各誌紙でとりあげられ、好評裡に版を重ねた。その後、『中国を知るために』は、昭和四十八年四月、第三集を刊行して完結した
竹内さんの書物も行動も、すぐに決定的な反響を生むというようなものではない。地にしみこむ水のように読者の心に沈んで、年月とともに次第に或る人達の間の共通の意識となり、理解となり、やがて行動の原理にまで定着してゆくといった感じのものである。
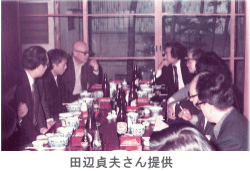
竹内さんには、信州生まれのガンコな気質と東京に育った繊細な市民感覚とが微妙に混ぜ合わさっているようだ。あのガンコで執拗な理屈好みは前者から、エセ権威に対する鋭い反発は後者からくるものだろう。私の接した竹内さんは、弱者に弱く、強者に強かった。名もなき人々との対話をつとめて心がけていたこともそこからくるものと思う。
人とのふれあいを大切にするといえば、病気になる半年ほど前だったか、『魯迅文集』の改訳に没頭していられた頃、旧普通社の著者が一夕集まって、病気がちの八重樫昊氏を囲む会を催したことがあった。その折も竹内さんはわが事のように喜んで、連絡をした私に、「どんなことでも手伝うからね」といい、当日、浅草伝法院近くの会場には、あの忙しい中を最も早く来てくださったのだった。
竹内さんが、「最近は疲れやすくてね」ともらされたのは、五十一年の夏に伺ったときだったと思う。そのころ私は、『新編魯迅雑記』の企画で、折をみては、吉祥寺のお宅を訪ねていた。けれども竹内さんは『魯迅文集』の改訳が追いこみで時間がとれないという感じで、もっぱら照子夫人と話すことが多かったが。
竹内さんの病気が重くなり、千駄木の病院に入院されたと聞いたのは、それからまもなくのことだった。ちょうど私の父も同病院の同じ建物に入院していたこともあり、私は何回となく病室を訪ねた。そのときはまだいろいろ話も出来たのだが……。
『新編魯迅雑記』が仕上ったのは、そうした入院中の一日だった。武田泰淳さんの後を追うように竹内さんが亡くなって一年余、命を賭けた仕事であった『魯迅文集』の発行元筑摩書房が倒産し、会社更生法が申請された。何か時代の転換といったような、奇しき因縁が感じられてならない。
竹内好著『中国を知るために』(全三冊) 各巻四六判上製、函入、二四〇頁、各一五〇〇円、第一集・昭和四十二年二月十五日、第二集
・昭和四十五年三月二十五日、第三集・昭和四十八年四月二十五日、勁草書房。*「竹内好全集」(筑摩書房)に収録。
竹内好(たけうちよしみ) 明治四十三(一九一〇)年長野県生れ。昭和九年東京大学文学部卒。同年岡崎俊夫、武田泰淳らと中国文学研究会結成、十八年解散。十九年『魯迅』刊行。三十五年安保条約国会強行採決に抗議し都立大教授辞任。四十一年『竹内好評論集』全三巻を刊行。五十二年個人訳『魯迅文集』刊行の中途にして死去。
『本の誕生─編集の現場から─』所載 (日本エディタースクール編 日本エディタースクール出版部 一九八一年九月二十五日発行)初出は月刊『エディター』一九七八年十一月号。
(表題の「熱っぽい著者の息吹」および末尾に記載された「竹内好の作品名・経歴」は単行本収載時に追加された。)
Copyright (C) Sadao Tanabe 1978 All Rights Reserved.