竹内好かく語られ記
回想・戦地体験
Tweet
回想・戦地体験
斎藤秋男
若ものはあまりしないかもしれないが、年の始めの "読み始め" ということがある。去年は、神谷美恵子『こころの旅』が "読み始め" だった。武者小路が死んだあと、この本がうしろのほうで武者さんをとりあげ、そこで "美しい晩年" ということをじつに美しく書いているのを、チラリとみていたことがあって、去年の元旦は、この本をはじめから読んだ。
ことし(七七年)は、岡倉天心『茶の本』を "読み始め" た。動機は、ハッキリしない。ただ、去年『こころの旅』という本に魅かれたのには、著者が「六〇が近づいて」自分の歩んできた旅路を自分なりにふりかえってみたい、というきもちがはたらいた、ということを書いている(ママ)、ひとつには、そこのところと結びついているかもしれない。
『茶の本』をわたしは、旧制中学二年の国語の授業で、田尾一一先生に教えてもらった。わたしの少年期に、東洋・アジア・中国へのイメージを形成させる、いくつかの要因に、この本があったのだ。
長いこと、それと気づかずにいたことが突然意識に蘇った感がある。中学生のころは、岩波文庫版で読んだが、いまではいろんな版がある。そして、竹内好「岡倉天心」を読みかえした。
竹内さんの書いた "評伝" では、「評伝毛沢東」(五一年四月)とならんで、この「岡倉天心」(六二年五月)がわたしは好きだ。明治日本の美術の世界で天心が発揮した "国粋" を、音楽のハタケで伊沢修二が推進した "文明開化" と対比させて、短い行文のうちに描ききっているあたり、見事というほかはない。毛沢東から天心へ、執筆時期に一〇年の隔たりがあるが、天心に立ちむかう筆者の気迫は、充実を持続しているとおもう。
ことし一月は、関西の友人との約束があって、二〇日すぎ、もとめられるままに「中国文学研究会の想い出((1))」を書いた。ウカツなことにわたしは、竹内さんの病気が篤いことを、長いこと知らずにいた。知らぬまま書いた "想い出" の載った雑誌がとどいた日の夜、保谷に住む友人から電話をもらい、吉祥寺・森本病院へ出かけたのは、二月二二日夕のことである((2))。
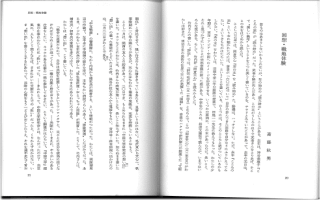
"中支戦線" の警備隊に、ちかく内地から補充兵が到着する、という情報がつたわった。わたしは、洞庭湖周辺の作戦で、左半身に手榴弾の破片を浴び、半年ちかい病院ぐらしのあと、 "原隊復帰" したばかりだった。
ある日、イジのわるい古年次兵の評した "厚生省派遣・おとっちゃん部隊" が到着した。こうして、竹内さんは、補充兵・初年兵の軍装を身につけて、わたしのまえにあらわれたのである。
わたしは "想い出" で、こう書いている。
「戦争の進展のなかで、自分は兵役を延期しているというウシロメタサと、日ごとに自分を破局に投じなければならぬときが迫ってくる、一種の自棄と居なおりがあった。……兵隊にいくまえに、やりがいのある仕事をしたい、ネウチのある仕事の一端に参加しておきたい(ママ)、こういう願望がはたらいて、『中国文学』編集の仕事はわたしには "救い" だった。
……きみにとって、中国文学研究会とは、なんだったのだ? 当世風に、人もしこう問うならば、さきにひいた文脈のうえでの "救い" だったと、くりかえすほかはない。
いま "想い出" を書こうとするにあたって、当時の心情をもう一どよびおこしたうえ、それを過不足なく言おうとすれば、こうした言いよう以外にない、とわたしはおもう」
中国文学研究会は、戦争へ出かける日を前にしたわたしにとって "救い" だった。会をひきいる竹内好は、わたしにとって "救い主" だった。そのほぼ三年の後、戦争のなかで、わたしは現役・古年次兵であり、竹内好は補充・初年兵の境遇で再会したのだった。
わたしにできたことといえば、警備隊駐屯地で、日本人商人が売る大福(マンジュウ?)を買って、竹内二等兵にとどけたことぐらいである。照子夫人の話によれば、危篤状態のつづく病床で、「サイトウに敬礼するのはシャクだなあ。シャクだけど、仕方がないなあ――」と口走っていたという。シャクだったろう、そうだろうなあ、とわたしはおもうばかりだ。
いま、こう書きながら、自分のこころが鬱屈していくのを感じる。そして、幻覚ではなく醒めたこころで、竹内好は自身の戦地体験をどう語っているか、確かめておきたいとおもう。それには、高橋和巳との対談をひきあいにだすのがいいだろう(六九年三月。対談集『状況的』)。
高橋が「中国文学の勉強というのは、戦後の状況とちがって、非常な苦衷があったのじゃないか」とたずね、これに竹内が「それをどういうふうに説明したらいいかがよくわからないんだな」と思案しつつ「私の場合は、それを戦後になってからある程度自己解明している。それは一口でいうと、それは結局弱い者への共感ということになる」こうしたやりとりのあと、 "中国に兵士として行くことの意味" という小見出しの部分がある。
そこでの発言は、こうである。
「……侵略戦争であるというような規定からくる痛みよりももっとちがうもの、弱い者いじめであることがいやなんです、自分もそういう位置にいることがね。私はこれは言いたくないのですが、白状すると、鉄砲を一ぺんも撃ってない。それは偶然そうなったんですがね。しかしそれによって救われている。歩兵ですから当然戦闘に参加したけれども、作戦のとき私は命令受領という特別の役についたので、鉄砲は撃たなかった。撃ったあとの現場は見ています。胴体の半分から下は何もなくなってしまった人間なども見ているけれども、自分では鉄砲を撃ってない。それが問題回避になっているのかもわからないけどね」
この発言の前後、話は当然のことながら武田泰淳の戦地体験とからみあって進行する。竹内さんがここで、兵隊として自分が直接には殺人に加担していないことを、一方ではそれで救われているといい、他方でそれが "問題回避" になっているのかも、といっている、この思索の構造には、武田泰淳の短篇「審判」が確実に影を落している、とわたしはおもう。
復員。帰国後の比較的早い時期の竹内さんに、「軍隊教育の問題性」(五一年四月。『新編日本イデオロギイ』所収)と「屈辱の事件」(五三年八月。『日本と中国のあいだ』所収)という、戦地体験を基礎においた二つの文章がある。
"中支戦線" で敗戦直後、竹内一等兵がじかに自分がきいた中隊長の訓辞、訓辞につづく「軍人勅諭」斉踊のエピソードを、両方の文章でくりかえし語っている。
「我国の稜威振はざることあらば汝等能く朕と其憂を共にせよ」
整列した兵士の群のなかにあって、自分は「胸が苦しくなった」と書き、また、あとの文章で「これは私にショックであった。単なる修辞として何げなく読み過していた勅諭に、この緊迫した表現がふくまれていたことを知って、明治の精神を改めて見なおした気がした」と書いている。
この元日に『茶の本』を読み、竹内「天心」を読みかえした、とはじめに書いた。たとえば「天心をファシズムと切り離すことは、そうむずかしくないが、 "日本ロマン派" 的解釈と切り離すことは案外簡単にはいかない。
……彼にはもっと多くの可能性があった」というくだりを読むとき、天心の可能性をひきだそうとの意図は、竹内さんに強烈にはたらきつづけていた "明治の精神" の可能性探求、その課題・作業の一環であったことは疑えない。
エピソードの主人公は、竹内さん自身が書いているように、竹内二等兵を帯剣でぶんなぐり、土手の上から突き落した男だ。中隊がちがい、直接の上官ではないが、わたしもよく知っている。この男の提供した素材に、竹内さんはただちに "明治の精神" を「見なおした」のだ。わたしは、竹内好の戦地体験の記録に、これを書きこんでおきたいとおもう。
大日本帝国の軍隊に "現地除隊" という制度(?)があった。わたしは同じ中隊の戦友二人と語らい、これを利用して軍隊を離脱した。洞庭湖にそそぐ河にそった港町から、岳州を経由、漢口に出た。新聞社に住みこんでほぼ一年後、上海から浦賀に上陸、焼けあとの東京にたどりついた。
竹内さんは岳州の司令部で敗戦、「戦争終わったらすぐ、現地除隊して、兵隊でなくなって、しかしそれじゃ食えなくて、軍属部隊へはいって通訳したんです。その鉄道隊といっしょに帰ってきたんですよ」と語っている
(松本昌次さんとの対談、六九年二月。前掲『状況的』)。
わたしは岳州の通りすがりに、軍服をつけた男に竹内さんの消息をたずねた。「竹内は、おれたちとは反対に、重慶へ行きたい、重慶へ行くんだといっているらしい。重慶がムリなら長沙まででも行ってみる、といってるそうだ――」
そんなバカなことをいわずに一しょに復員しろ、といった周囲の制止をきかずに、竹内さんは岳州から、みんなとは反対の方向へ歩きはじめたのではなかったか、とわたしは想像する。鉄道隊とめぐりあったのはどこです? いつか問いただすつもりでいたのだが、もはや、その機会がない。(七七・一二・五)
注(1)「中国文学研究会の想い出」、雑誌『咿唖』第七号、小文の日付け七七年一月二五日、発行日付け七六年一二月三一日
注(2) 森本病院でのあれこれについては、別に書いた。「幻覚のなかの "8・15" 」、大宮信一郎氏編集『竹内好回想文集』。
『追悼 竹内好』(竹内好追悼号編集委員会編集 魯迅友の会1978年発行)所収
この文章の掲載にあたっては、斎藤淑子さんのご了解をいただきました。
Copyright (C) Toshiko Saito 1978 All Rights Reserved.